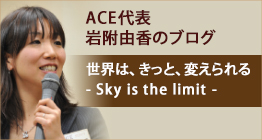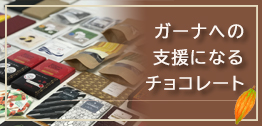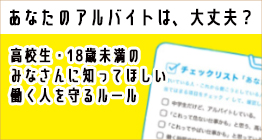「プロジェクト終了後も活動を続けていきたい」住民の声とプロジェクトの参加型評価の様子をお届けします!
みなさん、こんにちは!インド・プロジェクトマネージャーの森です。 いつもACEの活動への温かいご支援をいただき、ありがとうございます。
ACEは、インド・テランガナ州のコットン生産がさかんな農村地域で、現地パートナー団体SPEEDとともに、児童労働から子どもを守り教育を支援する「ピース・インド プロジェクト」を行っています。
今回のインド便りは、オンラインでのモニタリングで聞こえてきた現地の声と、これまでプロジェクトで活動してきた村で行った参加型プロジェクト評価の様子をお届けします!
参加型プロジェクト評価とは、受益者を含めた幅広い関係者(ステークホルダー)が、評価プロセスに参加し、プロジェクト理解、当事者の意識向上、能力開発などを通じてエンパワーメントされ、事業・組織の改善に貢献することができる評価アプローチです。
モニタリングで聞こえた住民の声
2023年4月14日、プロジェクト活動地の村と中継を行い、子ども、教員、住民の声を聴きました!プロジェクトで運営するブリッジスクール(児童労働から解放された子どもの公立学校への就学を支援する補習学校)に、子どもたち、住民ボランティアメンバー、職業訓練センターの教員、現地パートナー団体SPEEDのスタッフが集まってくれました。

子どもたちが元気に挨拶してくれる様子に、私も笑顔になります。
7歳から11歳までコットン畑で働いていた12歳のビマラさん(仮名)は、「コットン畑の仕事は手作業が多く、手のひらが固くなってしまい、今でも柔らかくならない。」と話しながら手のひらを見せてくれました。
そんなビマラさん、以前はシャワーを浴びることがあまりなかったそうですが、家庭訪問や集会での啓発活動を通して親が健康について考えるようになり、ブリッジスクールに通う現在は、シャワーを浴びることができるようになり、親が朝食を用意してくれるようになったそうです。

7歳から11歳までコットン畑で働いていたビマラさん(仮名)
すべての村で実施したプロジェクト評価
「ピース・インド プロジェクト」は、これまで10年以上にわたり6つの村で活動を実施してきており、そのすべての村を対象として、プロジェクトの有効性や実際に「児童労働のない村」が維持されているかを調査するため、それぞれの村で受益者やステークホルダーの声を聞き取るインタビューを行いました。

インタビューを受ける子ども(中央)と母親(左奥)

インタビューを受ける職業訓練を受けた女の子(写真左)

子どもの両親へのインタビューの様子

住民メンバーへのインタビューの様子
子ども・住民の声
以前はコットン畑で働いていて、ブリッジスクールに通うようになったアンシュさん(仮名)は、「プロジェクトの実施によって子どもたちの変化は見られますか?」という質問に、「以前は両親から働くように言われていたが、両親が子どもの教育が大事と理解し始めたから、ブリッジスクールに行けるようになった」と答えてくれました。

インタビューに答えるアンシュさん(仮名、写真中央)と両親
また、「村で開催されたお祭り※で、児童労働が法律違反であることを知った」ことも話してくれました。
他にも、「以前は自分の周りのほとんどの子どもがコットン畑で働いていたけど、今はその子どもたちも学校に通っている」「今は毎日学校に行っているから、良い教育を受けていると思う」「以前は学校にトイレがなかったから学校に行かないこともあったが、今はトイレが整備された」という声も聞かれました。
子どもたちの意識の変化はもちろんですが、親の意識や子どもを取り巻く環境の変化が子どもの教育に影響を与えていることが見えてきました。
仕立屋になるための職業訓練を受けたアリア さん(仮名)は、「プロジェクトが実施されてから、女の子に対する村の人たちの意識が変わり、特に親の考え方が変化したと思う」と話してくれ、「子どもの権利を知っていますか?」という質問には、「はい、知っています。 Right to Freedom, Right to protect, Right to live (自由の権利、守られる権利、生きる権利)」とはっきり答えてくれました。

インタビューに答えるアリアさん(写真右手前)と見守るお母さん(写真右奥)
一方で、今回のプロジェクト評価を通して、これまで活動を終了した村で、コットン畑に戻って働いている子どもがいるというケースも報告されました。特に繁忙期の7月、8月になると、一時的に学校に行かずに、コットン畑に戻って働く子どもがいることが確認されたのです。
そのようなケースに対して、私たちはどのような方法をとるべきか常に考えさせられます。
オンラインでのモニタリングやインタビューを通して、児童労働から抜け出すきっかけとしてよく聞かれたのが、住民ボランティアメンバーの活動の重要性とその活動の効果です。
メンバーが家庭訪問や家族との話し合いを続けたことが、子どもや親、住民の意識の変化に大きな役割を果たしていることが改めてわかりました。

自分の活動について話してくれた住民ボランティアメンバー
村で住民や子どもとの話し合いを自立的に行うメンバーは、こう話してくれました。「自分は3年間活動していますが、当初22名いたメンバーが15人になり、今は新しいメンバーを探すのに困っています。ただ、15人いるメンバーは一生懸命取り組んでいて、活動に意義を感じています。自分の村が変わっていく様子も嬉しく思っています。プロジェクト終了後も新メンバーの勧誘をしながら、活動を続けていきたいです。」
「児童労働のない村」を維持する仕組みの重要な要素となるのが、住民メンバーの自立的、継続的な活動です。長期の活動となると途中で抜けてしまうメンバーもいるという課題もありますが、メンバーが寄せてくれたこの心強い言葉を励みに、活動を続けていくことのできる仕組みづくりをプロジェクト終了までにしっかりと構築したいと思います。
現地では今後も、全ての子どもが教育を受け、「児童労働のない村」を維持できる仕組みの構築のため、住民に寄り添いながら、自立を後押しする最善策を検討し続けます。
引き続きの応援をどうぞよろしくお願いいたします!
※教育の重要性や児童労働について啓発する子ども向けのイベント
インド・プロジェクト マネージャー 森
インドの子どもたちを笑顔にするために
応援よろしくお願いします!
- カテゴリー:報告
- 投稿日:2023.05.24