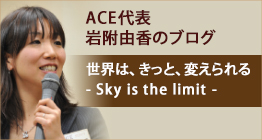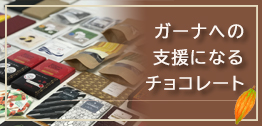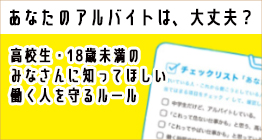【開催報告】院内集会「児童労働ゼロ、その日はいつ?」~SDG 8.7 児童労働撤廃目標期限の 2025 年の今、私たちにできることは?~
【開催報告】院内集会「児童労働ゼロ、その日はいつ?」~SDG 8.7 児童労働撤廃目標期限の 2025 年の今、私たちにできることは?~
ACEが事務局をつとめる児童労働ネットワークは、国連が定めた「児童労働反対世界デー」にあたる6月12日、国会議員会館にて院内集会を開催しました。

写真提供: 児童労働ネットワーク
児童労働者数は減少するも、撤廃まで道半ば
2025年はSDGsの目標8.7に定められた「あらゆる形態の児童労働を撤廃する」ことの達成目標年。しかし、6月11日にILO(国際労働機関)とユニセフから4年ぶりに発行された推計によると、世界の児童労働者数は1億3800万人。推計を取り始めた2000年には2億4600万人だったので、その半分程度にまで減少しましたが、世界中の子どもの13人に一人がいまだ児童労働に従事している現状です。2015年に世界中がSDGsの目標として子どもたちに約束した「児童労働ゼロ」は果たされていません。
取り組みの強化・拡大を!
―国会議員の方々と児童労働の課題や連携可能性を共有
国による児童労働撤廃のための様々な政策の強化・拡大を促すべく、法務大臣、厚生労働副大臣、外務副大臣のほかたくさんの国会議員をお招きし、「児童労働ゼロ、その日はいつ?」をテーマに、以下の内容を実施しました。
①ILOとユニセフから発行された最新の推計内容と政府への提言内容の共有、
②産官NGOによるステークホルダー連携の事例にしたパネルディスカッション、
③様々な形態の児童労働から子どもたちを守る活動をしているNGOなどからの児童労働撤廃に向けたコミットメント発表
これらを通し、国内外の政府関係者、NGO、企業、メディア、そしてユースが、現状の課題や児童労働撤廃に向けた連携可能性について意見を交わしました。
より効果的な連携に向けて
―「今までの11倍のペース」に少しでも近づけるために
院内集会の中で、児童労働をなくすためには「関係者が連携することが重要である」ことが幾度となく繰り返し強調され、この院内集会に参加した全員が共通の認識をしたことと思います。しかし、登壇者から課題として共有された、「連携を進めていく上で必要な情報がなかなか出てこない」「調整に時間がかかる」など経験に基づく発言にみられるように、もどかしい面があるのも事実です。
2030年までに児童労働をなくすには今までの11倍のペースでの取り組みが必要とILOとユニセフは訴えています。ACEも、ガーナと日本で様々なプロジェクトを多様な方と連携して行っています。国内外の関係者と知見や経験を共有し、より効果的な取り組みを実施できるよう邁進してまいります。また、日本政府による取り組みがより実効的なものとなるよう、これからも外務省と始めとする省庁へ働きかけを続けています。
以下、院内集会の様子を詳細報告です。長いですが、ぜひお読みください。
◆第一部◆
開会あいさつ
児童労働ネットワーク 代表 堀内光子
皆さんこんにちは。児童労働ネットワークの代表をしております堀内光子でございます。本日はお忙しい中おいでいただきましてありがとうございました。ILO活動推進議員連盟会長でいらっしゃいます田村先生にもおいでいただきまして、本当にありがとうございます。また、UNICEF議員連盟牧島先生にもおいでいただき本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
本日は皆さんご存知かもしれませんが、国連が定める児童労働撤廃の世界デーでございますのでぜひこの日を機会に、子どもたちが子どもらしく過ごせるような活動をみなさんとご一緒に強化して参りたいと思います。本日は長丁場になりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
ILO 活動推進議員連盟 会長 田村憲久 衆議院議員
ご紹介いただきましたILO活動推進議員連盟会長の田村憲久です。
今もお話にありました、今日は児童労働反対世界デーということでございます。国会内で児童労働撲滅の非常に重要な集会を開催いただきました。心からお招きいただきまして感謝を申し上げます。世界には今なお1億6000万人を超える児童労働を強いられている子どもたちがいるわけでありまして、本当に教育の機会を奪われ、また過酷な労働環境の中で働いています。
我が国では比較的多くの子どもたちが学びや遊び、自由な時間を確保できているわけですが、世界にはそのような時間をしっかりと確保できない子どもたちが多くいるということ。我々は改めて認識をしなければならないと思います。
我が国においても、色々とアジア太平洋地域においてILOと協力しながら児童労働撲滅など活動しているが、児童労働という問題はグローバルな経済・社会の中において、他国の問題ではなく、我々にもかかわっている問題だと認識しております。グローバル経済ですから労働もその中に組み込まれているため、普段輸入して使っている製品の中にも児童労働が関わっている、隠れている、そのような問題が多々あり、我が国のことのように考えていかなければなりません。
特に経済界の方々に関して、「ビジネスと人権」、「人権デューデリジェンス」というような形で認識をいただき、児童労働、劣悪な労働を是非とも経済活動から切り離していただきたく、様々な努力をいただいておりますし、さらにそういうことが成果として現れるように期待しております。
我が国は令和5年に、こども基本法を作りました。この中には、すべての子どもたちが身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることで実現できる社会と言うものを目指しているわけで、この想いは我が国のみならず、世界の子どもたちに対して我々はこの想いを持っております。そのような意味で、児童労働というものが撲滅されて、世界の子どもたちの輝く笑顔が保障されるような社会をつくっていくために、我々ILO活動推進議員連盟も微力ではございますが努力して参りたいと思っております。
本日は成果の出る集会になりますことを心からお祈り申し上げます。
ユニセフ議員連盟 事務局長 牧島かれん 衆議院議員
ユニセフ議員連盟事務局長の衆議院議員牧島かれんです。
ユニセフ議連でも児童労働ゼロを一日も早く世界中で実現するようにという思いで共に活動させて頂きたいと思っております。ユニセフ議員連盟では先日外務大臣のところに要望に伺いました。その内容は日本からユニセフへの拠出をしっかりと行うことによって世界中の子どもたちを守っていきたい。今、国際情勢が大変厳しくなる中で命を守ることすらままならない子どもたちがいます。学校に行きたくても行くことができない女の子たちもいます。また、病気になっても治療薬が届かないという状態にもなりつつある。そうした危機感のもと、子どもたちの人間の尊厳を守るためにユニセフ議員連盟としても国内にて国会議員超党派で活動を続けております。
また昨日こども家庭庁の大臣のところを訪問した際、子どもたちの寄せ書きのボードがあり、自分がもし大臣になったらやってみたいことが書かれていました。その中に「世界中の子どもたちに関心を持つ」と書いてくれた子どもがいたことが私たちの心を動かしました。自分たちの周りだけではなく、世界の子どもたちのことにも興味を持つ日本の若い世代が育ってきている、SDGsの教育を受けている子どもたちもいるということを心強く思いながら、これが児童労働ゼロにつながるようにと私たちは加速させなければならないと思います。
そしておとなたちも含めてこの商品やサービスがどのように届けられたのか。その生産の過程に児童労働はなかったのかということを考えて手に取ることができるような消費者でありたい。または、消費者教育というものも進めていきたいと思っています。
一緒に力を合わせて参りましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
来賓の方々からのメッセージ発信とコミットメント
仁木博文 厚生労働副大臣
厚生労働省の副大臣仁木博文と申します。
本日は児童労働反対世界デーであるこの日に、多くの関係者のご参加のもとこのような院内集会が開催されますことを心よりお祝い申し上げます。また本集会の開催にあたりご尽力されました児童労働ネットワークみなさまに深く敬意を申し上げます。
児童労働は様々な価値観や立場が交錯する、国際社会が一致して取り組んできた課題です。このことは最悪の形態の児童労働の禁止撤廃を定めたILO第182号条約が、数あるILO条約の中で唯一全ての加盟国が締結する条約であることにも表れております。それにもかかわらず、世界の児童労働の撲滅には至っていません。
我々はILOが掲げる一部の貧困は全体の繁栄にとって危険であるという理念を今一度思い起こし、更に行動を重ねていかなければなりません。一国の目先の経済的な利益のみに取られているのではなく、世界中の誰一人として取り残さない持続可能な世界を目指すことが必要です。
厚生労働省ではILOとの協力のもとアジア地域を中心に児童労働の撲滅に向けた取り組みを進めてまいりました。例えばネパールでは、現在児童労働に関する国家基本計画の見直しのための技術支援や児童労働に従事する子どもの救助・保護・社会復帰の推進などに取り組んでいます。またILO駐日事務所と共同で労働におけるビジネスと人権チェックブックを作成しました。これは企業に対し、児童労働を含む中核的労働基準の尊重を日々の業務の中でどのように実践すべきか、わかりやすく示すものとなっています。
児童労働は単なる労働規制の問題にとどまりません。それは子ども一人ひとりの尊厳をどのように守るかという問いです。子どもは可能性に満ちた存在です。彼らの持つ可能性を社会が明るく照らしてくれるものにするのは教育です。児童労働は子どもが教育を受ける機会を奪い、社会から輝きを失わせるものです。厚生労働省はこれからもILOと協力して、児童労働の撲滅に取り組んでまいります。
本日の集会が関係の皆様方をより一層強く結びつけ、児童労働のない世界を共に切り開く契機となることを心から願い、私のご挨拶とさせていただきます。令和6年6月12日厚生労働副大臣仁木博文。
宮路拓馬 外務副大臣
外務副大臣の宮路拓馬です。本日はお招きいただき誠にありがとうございます。外務省を代表して一言ご挨拶申し上げます。
本日の主題である児童労働は、SDGsの目標8.7において、「2025年までにあらゆる形態の児童労働を撤廃する」ことが掲げられているように、教育を含めた児童の権利を侵害し、その子ども時代を奪うとともに、心身の健全な成長を阻害する深刻な問題です。2002年にILOが「児童労働反対世界デー」を定めてから、今年で23年が経とうとしています。しかし、児童労働の撤廃には未だ多くの課題が残されており、こうした課題の解決は、私たち社会全体の責務です。
サプライチェーンにおける児童労働等の撤廃を含め、企業活動における人権の尊重を促進することが求められています。2020年に我が国で策定された「ビジネスと人権」に関する行動計画においても、児童労働を含む子どもの権利の保護・促進は横断的事項の一つとなっています。
我が国はこれまで、ODAやILO等の国際機関への拠出などを通じて、児童労働の撤廃につながる教育や人身取引対策といった分野の取組を支援してまいりました。
JICA (Japan International Cooperation Agency)は「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォームの事務局を務めています。2021年9月に「児童労働の撤廃に向けたセクター別アクション」を定め、企業、NGO、政府機関等、ステークホルダーの連携による取組を推進しており、その進捗報告を翌年から行うなど、途上国における児童労働の撤廃を目指した取り組みを継続しています。
ガーナにおいては、2024年1月から、国家計画として進められている「児童労働フリーゾーン(CLFZ: Child Labour Free Zones)」制度の強化と普及を、JICAによるプロジェクトを通じて支援しており、ユニセフやILOと連携を強めています。
外務省は、本年3月、ガーナでの脱炭素化、廃棄物削減に寄与するバイオ技術の普及を通じ、カカオ農民の生活向上支援、及び「児童労働フリーゾーン」制度を推進するILOのプロジェクトに約2億円を拠出しました。
外務省としましては、引き続き各府省庁、ILO等関連国際機関と連携し、またステークホルダーと継続的な対話を通じて、児童労働の撤廃に向けた取り組みを進めていきたいと思います。本日はありがとうございました。
鈴木馨祐 法務大臣(第二部で発言)
皆さんこんにちは。ご紹介いただきました法務大臣の鈴木馨祐でございます。本日は院内集会の開催、誠におめでとうございます。
ACEさんとも非常に長いお付き合いをさせていただいておりますけれども、我々法務省もビジネスと人権の中でそれぞれの企業のサプライチェーンの中でのこうした児童労働を含めた人権についての確認や徹底も図っていけるように経産省とほかの政府の関係機関とも連携をしながらそうした取り組みを進めているところであります。
法務大臣の前は、党にて企業の会計の関係の仕事を長く責任者としてやっておりまして、企業の情報開示という中で、やはり投資家サイドから特にTo Cについては、そうしたリスクが非常に大きいのがサプライチェーンの中での人権問題でもあろうかと思います。そうした中で企業の皆さんもこうした会議で様々なディスカッションいただいて、これからも更なる児童労働の撲滅に向けての取り組みの良いきっかけとしていただければ大変ありがたいと思っております。
引き続きこうした取り組みをさらに日本国内だけではなくて、世界の中でもさらに促進されることを心からお祈りを申し上げながら、我々としても政府としてもそうした取組をしっかりと後押してまいりたいと考えております。引き続きご指導ご鞭撻いただければ大変ありがたいと思っております。
改めまして今日のご参加の皆様方のご活躍、そしてこの会の成功を祈念申し上げまして簡単でございますけれども私からのご挨拶とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ジェネヴィーヴ・エドゥナ・アパルゥ ガーナ共和国駐日大使
どうもありがとうございます。私はガーナ大使のジェネヴィーヴ・エドゥナ・アパルゥです。この意義深いイベントに参加できることを大変光栄に思います。
ガーナでは、貧困が児童労働の最も重大な根本原因のひとつです。例えば、5歳から14歳の子どもたちのうち約25万人、全体の3.2%が経済活動に従事しており、その約80%が農業関連の仕事に関わっています。問題は農村部で特に深刻で、その発生率は著しく高くなっています。このためガーナでは、カカオ産業や炭鉱、漁業分野を中心に、戦略的な介入を行っており、目覚ましい進展を見せています。
ガーナは、国連子どもの権利条約やILO条約138号・182号といった重要な国際条約を批准しています。国内では、1998年のこども法や2005年の人身取引防止法といった立法枠組みが、児童労働対策の強力な法的基盤となっています。
さらに、児童労働を防止するための社会政策や制度を確立することを目的とした行動計画も導入・実施しており、2023年には児童労働に対する加速化行動計画を開始しました。主な重点項目には、質の高い教育へのアクセスの向上や社会的保護制度の強化が含まれています。
また、JICAやACEといったNPO団体、また特に児童労働が多く見られる地域の農民や漁業者と連携を深めています。なぜならば、農業はガーナ経済の基盤であり、その未来は持続可能性と人間の尊厳の尊重に根ざしているべきだと考えているからです。
私たちは、児童労働との闘いが共通の責任であることを認識しています。その意味でも、ガーナはパートナー、特に日本との連携を深め、成功モデルの拡大、教育の改善、農村の生活向上、そして子どもに優しいレジリエントな農業コミュニティの推進に引き続き取り組んでまいります。
結びに、これからも共に取り組んでいきましょう。すべての子どもたちが安全で幸せな子ども時代を過ごせるように。
第二部
第二部では、ILOとユニセフによる最新の世界推計をもとに、児童労働の現状と課題についての報告が行われたほか、カカオ産業の取り組みを事例としたパネルディスカッションを実施。企業、政府、NGOの登壇者が、それぞれの立場から連携のあり方や今後の方向性を共有しました。
「児童労働撤廃目標年」の今、国際機関の立場から見える世界の児童労働の現状と課題
ILO 駐日事務所 代表 高﨑真一
· 最新の世界推計によると、児童労働者数は2020年の1億6000万人から1億3800万人へと減少。危険な仕事に従事する子どもも、7900万人から5400万人へと減少。
· 当初はCOVID-19の影響で児童労働が増加している可能性が懸念されていたが、2000年と比較すると、子どもの総数が2億3000万人増加しており、それを踏まえても今回の減少は大きな成果。
· 地域別では、アジア太平洋地域が最も大きな減少率(4年間で45%減)を記録。アジア地域の一員として、日本としても誇りに感じる結果。
· 減少の主な要因:教育の確保と教育システムの整備・国際労働基準を含む法的保護の強化・社会的保護制度の拡充・サプライチェーン上の児童労働撤廃の取り組み。
· 1億3800万人という数字は、5歳から17歳の世界の子どもの約7.8%に相当(13人に1人が児童労働に従事している)このうち5400万人が有害な労働に従事。
· サハラ以南のアフリカでは割合は減少したが、絶対数は減少していない。紛争や脆弱な統治が児童労働に与える影響は大きい。
· 分野別では、農業が61%と最も多く、年齢が上がるにつれてサービス業や工業分野でも増加。男子が多数を占めるが、家事労働は女子の割合が高い。
· 児童労働に従事する子どもは、教育機会を失うリスクが非常に高い。
· SDGsでは2025年までの児童労働撤廃を掲げていたが、現時点で目標は未達成。
· 2030年までの達成には、現在の11倍のスピードで取り組む必要がある。
パネルディスカッション:アフリカの児童労働に市民・企業・政府はどう取り組めるのか〜課題・取り組み・希望〜
パネルディスカッションでは、カカオ産業における児童労働の解決に向けて、企業・政府機関・NGOが果たすべき役割や連携のあり方について、モデレーター(株式会社オウルズコンサルティンググループ 若林理紗氏)の進行のもと、各登壇者がそれぞれの立場から課題と今後の方向性を共有しました。
議論の中では、株式会社ロッテの飯田智晴氏が、サプライチェーンにおける企業の責任に加え、企業間や他セクターとの連携の重要性を指摘。特に、開発途上国のためのサステイナブル・カカオ・プラットフォームを通じた非競争領域での協働の意義を述べました。
独立行政法人国際協力機構(JICA)の琴浦容子氏は、「規制」は有効としつつも、それだけでは不十分で、バランスが重要だと指摘。現場には企業・NGO・国際機関など多様な関係者が関与しており、各取り組みを効果的に統合するためには、政府のイニシアティブによる連携の強化が鍵だと語りました。
また、ACEの白木は、JICAと進める「児童労働フリーゾーン」の制度構築において、支援を効果的に届けるための設計のためには企業のサプライチェーンと行政サービスを総合的に整備する必要があると説明。その点で、企業との調達地などに関する情報共有が重要だが、個別対応に時間を要する点が課題と述べました。一方で、国際機関等との連携が進み、各レベルでの協働体制が整いつつあることに期待を示しました。
最後にパネリスト三者から、「企業も自社の力で出来るところの取り組みを進めていく。一社のみの力では手が届かない部分は、NGOや政府機関と協力して進めていきたい。」(株式会社ロッテ 飯田氏)、「児童労働者数に減少がみられたことは、それだけ世界中が頑張っている証拠。しかし、ガーナ国内外において現場のコーディネーションや更に取り組めることがあるに違いない。関連機関に携わって頂きながら、引き続き尽力していきたい。」(JICA 琴浦氏)、「現場で一番感じるのは、リソースがあれば必ず実現できることがあるということ。しかしながら、それらが本来必要なところに分配されていない点に課題を感じる。必要なところの見極めをし、大切な資源を届けたい。あらゆる人を巻き込み、子どもの声を聴きながらこれからも活動していきたい。」(ACE 白木)と、児童労働撤廃に向けたコミットメント表明をし、議論を締めくくりました。
第三部
第三部では、政府関係者やNGO、ユースなど多様な立場の登壇者が、それぞれの現場での経験や取り組みをもとに、児童労働の現状と解決への道筋について語りました。法制度、教育、企業責任、当事者支援など、さまざまな視点からの発言を通して、課題の複雑さと連携の重要性が浮き彫りとなりました。
ドイツ大使館 労働・ヘルス・ジェンダー平等・人権担当参事官 ティモテウス・フェルダー=ルセッティ氏
「対話は非常に重要であり、ときに『法的な枠組みの制定を後押しする力にもなる』」と述べ、児童労働撤廃に向けた法制度の意義に触れました。ドイツでは、企業に人権デューデリジェンスを求めるサプライチェーン法が施行されており、「法の力を通じて企業の責任ある行動を促すことが児童労働撤廃の推進力になる」と強調。さらに、ドイツがAlliance 8.7のパスファインダー国として進捗報告や国際連携を進めていることを紹介し、「今後も市民社会との協力やアドボカシー活動を通じて国際的な協力体制の強化に貢献していきたい」と連携の重要性を訴えました。
外務省 国際協力局 専門機関室長 佐藤仁美氏
「2025年のSDGs目標8.7の達成は困難な状況にあり、政府、企業、そして多様なステークホルダーの連携が不可欠」であると強調。また、外務省がILOを通じて支援するガーナのプロジェクトでは、「児童労働フリーゾーンの推進と、カカオ生産者の所得向上を狙ったバイオ炭技術の導入による農業支援をかけあわせて、児童労働の撤廃を目指す」とし、「現地政府や関係機関との連携による成果が期待される」と述べ、関係者との協力を通じた課題解決への展望を語りました。
厚生労働省 大臣官房国際課長 平嶋壮州氏
厚生労働省はアジア太平洋地域でILOへの最大の資金提供者であり、児童労働撤廃に積極的に取り組んでいると述べ、その一例としてネパールで児童労働対策の国家基本計画見直しに向けた技術支援を行っていることに触れました。また、「児童労働フリーゾーン・プログラムの実施にあたり、労働に従事する児童の救助・保護・社会復帰を推進している」と言及。さらに、「ILO駐日事務所と共同で策定した『労働におけるビジネスと人権チェックブック』を通じ、企業の国際労働基準の実践を支援している」とし、「今後も関係者と連携して児童労働撲滅に取り組む」と述べました。
連合/公益財団法人国際労働財団 労使関係開発・草の根支援グループ グループリーダー パーワリン・チュンサム氏
「ネパールとインドにおいて、教育へのアクセスが限られた貧困層の子どもたちに基礎教育を提供するブリッジスクールプロジェクトを1996年から実施している」と述べ、労働組合の寄付によって運営される同プロジェクトの取り組みを紹介。また、教育の提供に加え、保護者への啓発や作文コンクールを通じて、地域での教育の重要性の浸透に努めているとし、「今後も現地の関係者と連携し、児童労働撲滅に取り組んでいきたい」と、継続的な取り組みへの意欲を示しました。
サステナリビリティ消費者会議 代表/CSO ネットワーク 代表理事 古谷由紀子氏
「かつて私たちも子どもだった。そして今、次の世代の子どもたちのために児童労働ゼロをどう実現するかは、すべての人の願いであり、同時に困難な課題でもある」と述べ、消費者の視点から児童労働問題に取り組む重要性を強調しました。さらに、「児童労働の実態を知らない」「自分とのつながりが見えない」「成果が実感できない」といった課題を挙げ、「意識に訴えるだけでなく、実際の行動につなげる仕組みが必要」と指摘。「多様な消費者に合わせた選択肢の提供や企業・NPO・自治体との連携、そして情報の可視化が鍵となる」と述べ、「世界中の子どもたちが自分の輝ける未来を描けるよう、力を尽くしていきましょう」と呼びかけました。
教育協力 NGO ネットワーク(JNNE) 副代表/公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 大野容子氏
「教育は児童労働から子どもを守る最善の投資」であり、「すべての子どもに質の高い無償教育を受ける権利がある」と強調しました。また、紛争や自然災害など緊急時においても教育は「メンタルヘルスや身の安全確保の仕方を教え、命を守る役割を果たす」と述べ、「こども兵や強制労働など最悪の児童労働から子どもを守るためにも教育の重要性は高い」と指摘しました。さらに、「多様なステークホルダーの連携が必要」であり、「国会議員には政策・現場両面での理解と協力を期待している」と今後のさらなる協力体制の構築を呼びかけました。
特定非営利活動法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン元FTCJ 子どもアンバサダー
植岡優里奈氏
「児童労働反対デーに合わせた啓発イベントや街頭募金」、「バースデイドネーションを通じた寄付の呼びかけ」、「フェアトレード商品の企画・販売への参画」など、これまで自身が実践してきた活動を紹介しました。そのうえで、「児童労働は国家や企業だけでなく、市民や若者も行動できる課題だ」と述べ、「これからも若者が児童労働の解決に向けてアクションを起こすことにコミットしていきたい」と語り、若者が主体となって行動することの意義を強調しました。
特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス 理事長 吉田真衣氏
アジア・アフリカの紛争地域で、元子ども兵の社会復帰や自立支援に取り組んできた活動を紹介し、「子ども兵の問題は、児童労働の中でも最悪の形態の一つ」と述べました。また、「私たちが活動する国々では、いまも多くの子どもたちが夢・希望・命までも奪われている」と現地の厳しい状況に触れ、「社会復帰だけでは足りない」として、2023年からはアフリカ中部現地のNGO・国際機関・政府と連携し、武装解除・動員解除の取り組みも開始したことを報告しました。最後に、「児童労働ゼロという日は、誰かが叶えてくれるものではなく、私たち一人ひとりの行動と連帯によって実現する」と述べ、継続的な取り組みへの決意を示しました。
特定非営利活動法人シャプラニール=市民による海外協力の会 事務局長 藤岡恵美子氏
バングラデシュやネパール、日本で活動する国際協力NGOとしての取り組みを紹介し、「アジア太平洋地域では児童労働が減少している一方、南アジアではいまだに大きな社会問題である」と述べました。特に、家庭内で働く子どもたちについて「工場と違って家庭の中で働く子どもたちは外から見えにくく、統計データもほとんどない」と指摘し、暴力や性被害の深刻な実態にも触れました。また、「現地社員や取引先が家庭で子どもを使用人として雇用しないよう、日本人として気にかける必要がある」と述べ、企業や個人の姿勢にも目を向けることの重要性を訴えました。
オープンフロア
質疑応答では、輸入国の責任や国際的な枠組みのあり方に関する問いが参加者から投げかけられました。まず、日本における輸入規制を含む法制度の必要性に触れ、「輸入国として、日本政府および企業はどのような責任を果たすべきか」との質問がありました。これに対し、企業の立場から株式会社ロッテの飯田氏は「人権デューデリジェンスの徹底と、リスクが明らかになった際の適切な対応を通じて責任を果たすべき」との意見が示され、 JICAの琴浦氏は「規制のあり方は各国の事情に即して議論すべきであり、日本独自のバランスを見極める必要がある」と述べました。またACEの白木は、「標準化という観点では規制の意義は大きいが、同時に煩雑性やコストの課題も欧州では見受けられる。実効性を担保するには、規制に加えて現場での取り組みを支える仕組みが不可欠」と強調しました。
また、会場に参加した高校生から、「国際法が存在するにも関わらず児童労働がいまだに根強く残る中、国際的な枠組みは今後どのような役割を果たすべきか」との問いがありました。厚生労働省の平嶋壮州大臣官房国際課長は、「児童労働の禁止は国際的に広く共有された認識だが、各国の状況に応じた取り組みとSDGsの理念に沿った総合的な支援が必要」と答えました。 児童労働ネットワーク 事務局長/ NPO法人 ACE代表の岩附は、 “児童労働がなくならない原因は、貧しさではなく、政治的意思の欠如によるものだ”というカイラシュ・サティヤルティ氏の言葉を引用し、「児童労働は途上国の日常生活の中で起こっているので一朝一夕になくすことは難しいが、様々な立場による児童労働を許さない継続的な意思とそれに伴う行動が重要。」と回答しました。
閉会あいさつ
児童労働ネットワーク 事務局長/特定非営利活動法人 ACE 代表 岩附由香
皆様、本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。
児童労働ネットワークは、堀内さんがILO駐日事務所代表だった2004年から活動を始め、NGOと労働組合がパートナーシップを組みながら、長年取り組みを続けてきました。署名活動を行い、そのうちの一つである「Alliance 8.7に加盟してほしい」という提案は2年前に実現しましたが、それ以外の部分では、まだまだ課題が残っています。
また、市民の皆さんにも児童労働の現状を知っていただこうと、今年も「レッドカードアクション」を実施しており、アクションに参加してSNS投稿をしていただくと、実際に児童労働に取り組んでいる団体への寄付につながる仕組みを設けています。
このように、児童労働ネットワークでは、NGOや労働組合の皆さんと連携し、世論啓発と政策提言の両面から取り組みを進めており、今回のイベントもその一環として本日の会を催させていただきました。
お忙しい中、皆さんにご参加いただいたこと、また多くの議員の方々にもご参加いただけたことを感謝申し上げます。児童労働撤廃の2025年の目標年には届かずという現状でございますけれども、諦めずにできるだけ早く、ひとりでも多くの子どもたちが児童労働から解放され、学校に行ったり遊んだりできるように私たち自身も力を入れながら活動して行きたいと思います。
皆さんどうぞこれからもご一緒に活動いただけますようお願いいたします。本日はありがとうございました。
- カテゴリー:報告
- 投稿日:2025.07.22