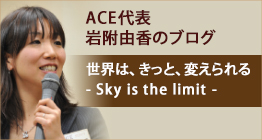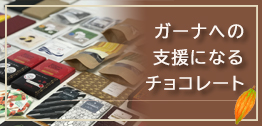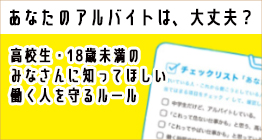【開催報告】児童労働白書2025年版を発行&発行記念セミナーを開催しました!
【開催報告】児童労働白書2025年版を発行&発行記念セミナーを開催しました!
こんにちは。マルチステークホルダー連携の推進を担当している川村です。ACEは児童労働問題の解決に向けて、ガーナの支援地と日本国内の双方で、NGOと企業の連携を促進しています。
10月27日に ACEは、株式会社オウルズコンサルティンググループとデロイト トーマツ コンサルティング合同会社とともに、児童労働に関する最新状況や企業に求められる対応などを包括的にまとめた「児童労働白書2025 ―ビジネスと児童労働―」を発行しました。児童労働白書の発行は2020年に続いて2回目、5年ぶりとなります。
同日、同書の発行を記念したセミナーを開催しました。「国連ビジネスと人権作業部会」議長のピチャモン・イェオファントン氏を迎え、世界の「ビジネスと人権」の潮流や日本の課題、企業への期待について聞くとともに、各領域でビジネスと人権に取り組む専門家のパネルディスカッションを行いました。
その様子を、ご報告します。
アーカイブ動画はこちらからご覧いただけます。
課題解決必要性の認識向上と、取り組みのより一層の加速を期待し発行
児童労働白書は、多数の報告書や実際の報道事例をもとに、児童労働の現状、ビジネスと人権の国際的な潮流、児童労働へ適切な対処を行わなかった場合のリスク、マルチステークホルダーにおける連携事例等を包括的かつ体系的にまとめたものです。企業経営者やサステナビリティ推進、購買部門等の実務担当者に加え、政府、NPO・NGO、学術機関など、幅広い方を読者の対象としています。
2025年版は、2020年版の内容を大幅にアップデートし、欧州のみならずアジアにおける人権デュー・デリジェンス関連法の整備を含むビジネスと人権の国際的な潮流を受け、より活性化されたマルチステークホルダー連携事例を多く取り込みました。課題解決必要性の認識向上と、取り組みのより一層の加速を期待し、連携における成果や学びを様々なセクターにおける活動に活かしていただけますと幸いです。
マルチステークホルダー連携の重要性を多角的な視点から議論
白書が発行された10月27日、都内にて、会場・オンライン合わせて約100名の参加者を迎え、執筆を行った3組織の共催で発行記念セミナーを開催しました。セミナーでは、白書の紹介に加え、ビジネスと人権を取り巻く国際的な潮流、日本政府や企業に期待されるアクション、企業が人権課題に取り組まない場合のリスク等が共有されました。また、マルチステークホルダーによる取り組み事例のひとつとして、ガーナにおける児童労働フリーゾーン認定制度の概要と進捗状況が紹介されました。
プログラム中ほどでは、「国連ビジネスと人権作業部会」議長 ピチャモン・イェファントン氏と、白書執筆各組織を代表し、岩附由香(ACE代表)、小野美和氏(デロイト トーマツ コンサルティング スペシャリストリード)、潮崎真惟子氏(オウルズコンサルティンググループ シニアマネジャー)の4名によるパネルディスカッションが行われました。参加者からの質問にも答えながら、企業による取り組みや官民連携の重要性について議論を深めました。

「国連ビジネスと人権作業部会」議長 ピチャモン・イェファントン氏(オンライン参加)
主要事業での取り組みにおける課題解決を
ACE代表の岩附からは、開発という分脈においても大きく課題のあるサハラ以南アフリカに児童労働が集中していることを共有し、児童労働のリスクの高い産品の代表例にカカオを取り上げ、日本で日常的に消費されているたくさんの産品が児童労働とは無関係ではないことを改めて強調しました。また、企業がSDGs達成に貢献する道として、主要事業にビジネスと人権の取り組みを組み込むこと、寄付(ソーシャル・インベストメント)や政策提言があることを紹介し、特に主要事業の中で課題解決に取り組む企業とACEの連携事例をいくつか紹介しました。
また、児童労働は企業にとっては、サステナビリティの観点、人権/CSR/ESGの観点、またリスクやブランド価値の観点、この3つの観点が重なる課題であると同時に子どもの権利の課題であることの視点を示し、世界的な人権尊重の流れを受け、現在ISOの世界でも、現代奴隷制やセーフガーディングに関する規格が検討されていることを共有しました。
※岩附は現代奴隷制に関するISO規格の策定プロセスの委員を務めています。
詳しくはこちら:ISO(国際標準化機構)で「現代奴隷制」に関する規格の検討が始まり、ISOエキスパートとして参加しました
日本国内にも存在する児童労働 ―求められる国内の制度整備―
パネルディスカッションでは、イェファントン氏の「児童労働を解決するためには、サプライチェーン上と国内の人権課題の双方に目を向ける必要がある」とのコメントを受け、岩附は10月初旬に17歳の若者が企業の社屋解体作業中に高所から転落し死亡した事故を例に取り上げました。国内で発生した児童労働は、現状事件や事故が発生してからしか表に出ず、また違反した事業者数でしかデータが分からない状態となっています。児童労働が日本の法律で位置づけられておらず、国内における児童労働の件数が「データなし」と長く続いているため、グローバルな指標に則ったデータ取得の運用や法の整備が求められていると主張しました。

出会うこと。それが連携の第一歩
最後に、「三者の協働を促進する上での最大の課題は何か?」という参加者からのご質問に対し、これまでのACEの様々な企業連携がどう始まったのかを振り返ったうえで「出会っていないことが最大の課題」としました。
実は、現在ACEがJICAの委託事業として取り組んでいるガーナにおける児童労働フリーゾーン構築の発端は、2020年の児童労働フリーゾーンのガイドライン策定にあり、このガイドライン策定には今回児童労働白書を共同執筆したデロイト、オウルズの皆様が関わっています。こうした協働が実現したのも、そうした協働機会が訪れる前に既に他の文脈で出会っていた、という現実があります。NGOの専門性などが企業側に見えにくい状況の中、連携を加速するための一例として、児童労働撤廃のためにオランダ政府が過去に実施した、連携パートナーに市民社会組織を関与させることを必須条件とした企業向け支援があったことを紹介し締めくくりました。
最後に
私も、イベント終了後のネットワーキングの時間に、会場にて参加された方々と情報交換をさせていただきました。その際、Aさんから聞いていた悩みに対し、Bさんが支援のスキルをお持ちであることが分かり、会場出口に足を向けるAさんをギリギリで引き留めてBさんをご紹介しました。イベントの場で今後の連携につながる可能性のある「出会い」が生まれたこと、大変うれしく思いました。
イベント後のアンケートにも、「共通の課題の解決を図る仲間に出会うことが重要だと分かった」などとの記述もあり、我々が直接連携をしているカカオ・チョコレート産業以外の方においても、連携の第一歩を踏み出すためのお手伝いができていましたら幸いです。
連携の手法はひとつではありません。本書には様々な連携事例が日本語でまとめられていますので、ぜひ共通の課題をもつステークホルダー間での連携手法を模索する際に参考にしていただければと思います。
今後も企業、政府、NGOなど様々な組織のみなさまと連携をして、児童労働をなくすための活動を進めてまいりたいと思います。これからも応援いただけますと幸いです。
マルチステークホルダー連携推進・政策提言担当 川村祐子
- カテゴリー:報告
- 投稿日:2025.11.21