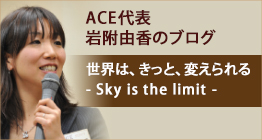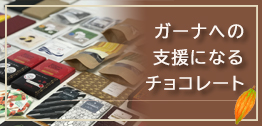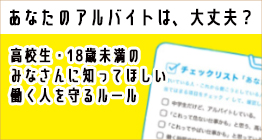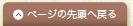2025年5月1日
【岩附通信vol.51】ぜんぶ、ホラクラシーのせいだ。
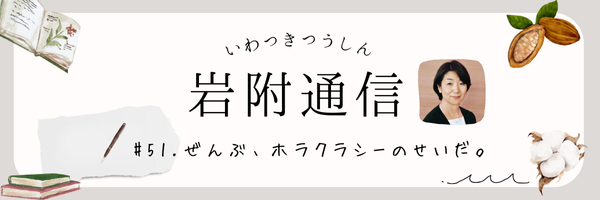
いつもACEへのご支援をいただきありがとうございます。
ちょっと体調を崩してお届けが4月になってしまいました。新年度、みなさまいかがお過ごしでしょうか?
お仕事の異動や転職、進学、お子さんたちの進学・進級に伴う生活の変化など、新年度に変化はつきものかな?と思います。みなさんは変化にどう対応していますでしょうか?
ACE事務局にも4月1日から新しいスタッフが2名、ジョインすることになりました。新しい方が加わるにあたって、いつも悩むのが、ACEの特殊な組織形態をどう説明し、どううまくon board (乗船する=乗組員の一員となる)していただけるか、という部分です。
この通信でも何度か書かせていただいていると思いますが、ACEはホラクラシーという仕組みを取り入れた組織運営をしています。
ボスはパーパスで、組織が鳥の群れのように動く。誰か特定のリーダーがひとつの方向にひっぱるのではなく、群れが有機的に動き、活動を推進して、渡り鳥のようにちゃんと目的地に着く。
組織形態としてはフラットで、それぞれのロール(役割)を持ち、そのロールのパーパスを実現していくことなら組織にダメージを与えたり、他の人の領域を侵さない限り、何をしても自由、という組織形態です。
もちろんNPOとしてガバナンス機構は必要なので、それもあわせもっていますが、日々のミーティングのなされ方などが手順が決まっており、特殊といえば特殊です。
ACEは現在この役割の明確化やミーティングの実施のために、Glassfrogというソフトウェアを使っていますが、先日、これと同じようなソフトウェアであるHolaspiritの創業者の方が来日され、ホラクラシーの実践者が集う会に参加させていただきました。
この場でホラクラシーを実践しているとお話を聞いていた団体さんや、あらたな企業の方々と出会い、交流を通じて多くの気づきをいただきました。
新しい方が組織にジョインされる際のOn boardingが難しいですよね、という話をしていた時のことです。経営者としてホラクラシー運営を我々よりずっと長くされてきた方から、私のその発言について、根本的な捉え方が違うかもなぁと感じた、というフィードバックをもらいました。
もちろん慣れるのに時間はかかるけど、自分は「出来る」って思っている、と。
それを聞いて、私が思ったことは、まわりから聞こえてくる「難しい」という声を、そのまま自分の感覚も通さずにただおうむ返しのように言葉にしていただけなんじゃないか、ということです。
本当に私は難しいって思ってる?って自分に聞き直してみたら、実はそんなに思ってないかも、ということに気づいてしまいました。難しいふりをしているだけだったかもな、とも。
今起きている課題とか難しいことも、ホラクラシーのせいじゃなくて、もともとあった課題で、でもそれがホラクラシー上で起きているから「ホラクラシーが難しい」と形容してしまうかもしれませんが、難しいと感じているのはホラクラシーの部分じゃなくて、別のことなんじゃないかな、ということに気づかされました。
そしてもうひとつ、「全体性」というのもキーワードとして浮かび上がってきました。「全体性」とは何か。ACEがホラクラシーを入れる前に、ティール組織について学ぼうと嘉村賢州(けんしゅう)さんを招いて教えていただいた研修のスライドには、ティール組織の本を書かれたフレデリック・ラルーさんの言葉としてこのように紹介されています。
「他人にどう見られているのか、どう受け取られるのか」を気にして身につけている「仮面」それを脱ぎ捨て、ありのままの自分(as a whole)として存在できる場。そういった場がある時、人々は仮面の裏に隠されていた「活力」「創造性」そして「情熱」を露わにします。そういった場、関係性の中では、自分すら存在していたのを知らなかった部分を探索し、自身をより深め、磨くことができます。
全体性のイメージ、つきましたでしょうか?
今回Holaspiritの創業者の方も「全ては会話からはじまる、会話をしている個人には、働く人としてだけでなく、親、子、友達などいろんな側面があり、そうした仕事以外の部分を切り離せるものではない」というようなことをおっしゃっていました。同じ賢州さんの研修スライド(だじゃれじゃないです)には、全体性に関連して「魂という野生動物を表に招く」というパーカー・パーマーさんの言葉も引用しています。
実はこのパーカー・パーマーさんの書かれた「全体性」に関する本を読みほどく「Active Book Dialogue」に参加して、いま読んでいます。そこにはメビウスの輪が自分が認識しようとしまいと、プライベートも仕事もすべては連続性の上にあることの象徴として紹介されていました。
そして、全体性の表出を助けたり、尊重するには、その人そのものを丸ごと受け入れ、信頼の輪の中で、その人を救おうとしたりなにかさせようとするのではなく、ななめ横ぐらいからの投げかけや刺激の機会を作りつつ、気づきが訪れるのを信じてそっと見守り待つことが大事なのかな、という気づきがありました。
しかしこういうことって、してもらった経験があればわかると思うのですが、経験もない中でなかなか難しいよな・・とも感じます。そこは、自分ができると信じて、そして自分自身がありのままでいることも、関係してくるのかな、と思いました。
4月からはじまる新しい場で何かをはじめられるみなさんにとって、その場が安心・安全で自分を出せる場になっていくといいな、そして新しくジョインされるお二人にとってもACEがそうなることを願って、2025年3月号(もう4月だけど)を締めたいと思います。
ビバ!新生活!
2025年4月2日 ACE代表 岩附由香
※「岩附通信」は、会員・子どもの権利サポーターの方の特典として毎月1回配信しているコンテンツですが、配信から一カ月以上が経過したものを代表ブログにて一般公開しています。
- « 過去の記事